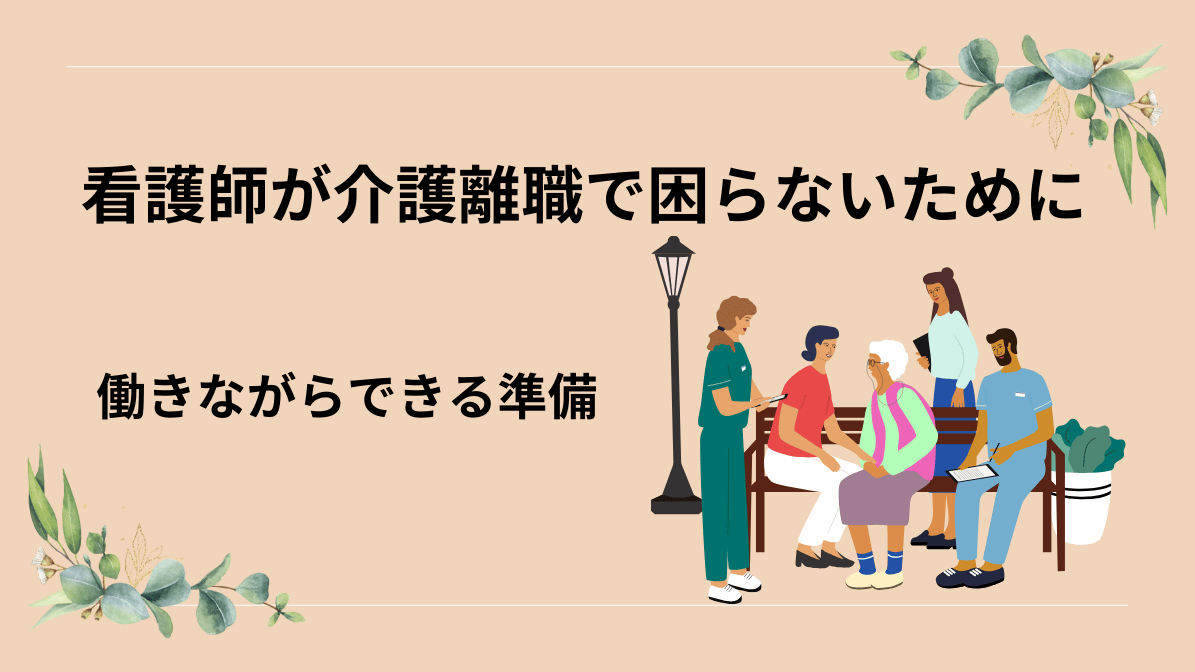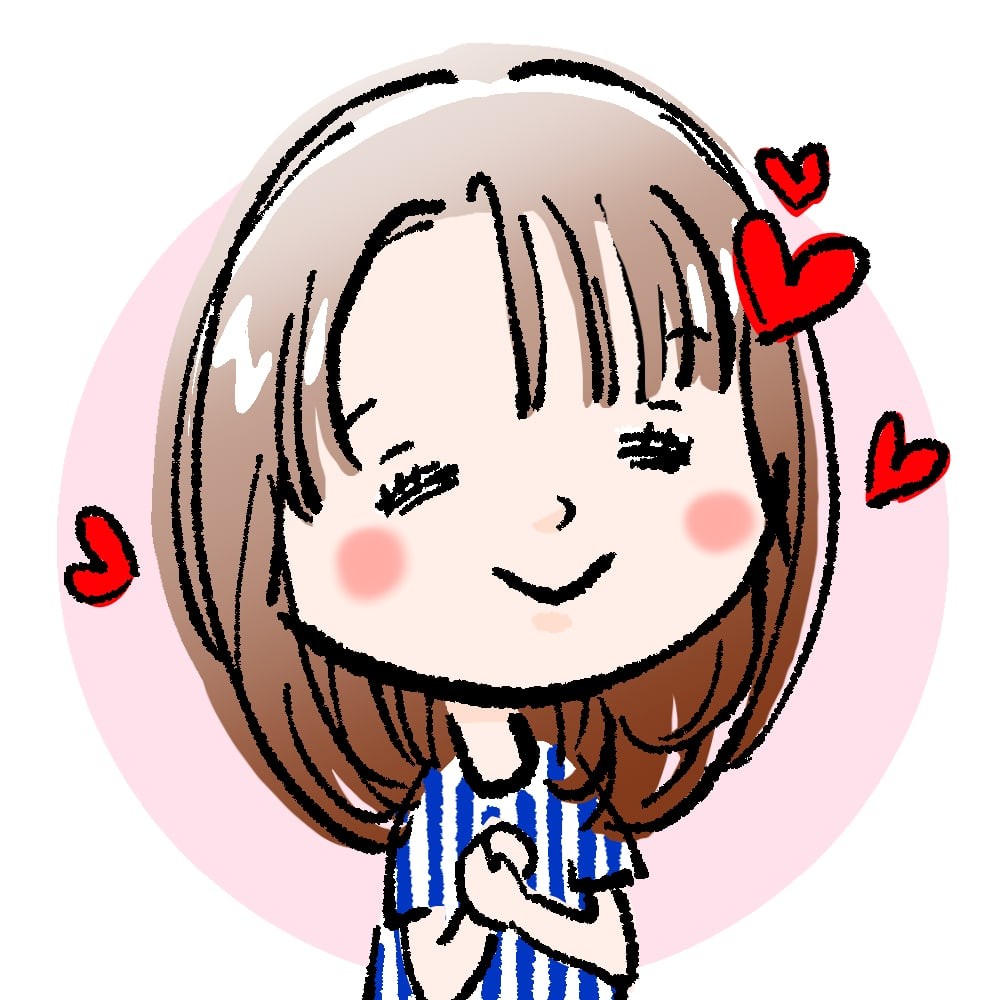はじめに
近年、看護師の介護離職が増加しています。高齢の親や家族の介護が必要になったとき、仕事と両立できずに離職を選択するケースも少なくありません。しかし、経済的な負担やキャリアの中断といったリスクを考えると、できるだけ離職せずに乗り切る方法を模索したいものです。本記事では、介護離職の問題点と解決策、そして看護師が働きながらできる準備について詳しく解説します。
介護離職の問題点

1. 経済的負担の増加
介護が必要になると、介護サービスの利用費用や交通費、介護用品の購入などで家計の負担が増えます。離職すると収入が途絶え、貯蓄を切り崩さざるを得ない状況に陥ることもあります。
50歳台のわたしは、子供が独立してようやく自分の自由を手に入れ、老後についても考えるタイミングで親の介護が視野に入ってきました。
決して親の介護のことを考えずに、今まで過ごしてきたわけではありませんが、自分の将来のお金の心配もあるので、正直、不安でしかありません。
親の資産を把握しているわけでもないので、もし自分のわずかな貯金を取り崩すことになれば、共倒れになってしまいます。
せめて、親の貯金や負債、年金受給額は把握しておきたいものです。お金のことだから、親子でもなかなか言い出しづらいこともありますが、把握しておかないといけないことだと感じています。
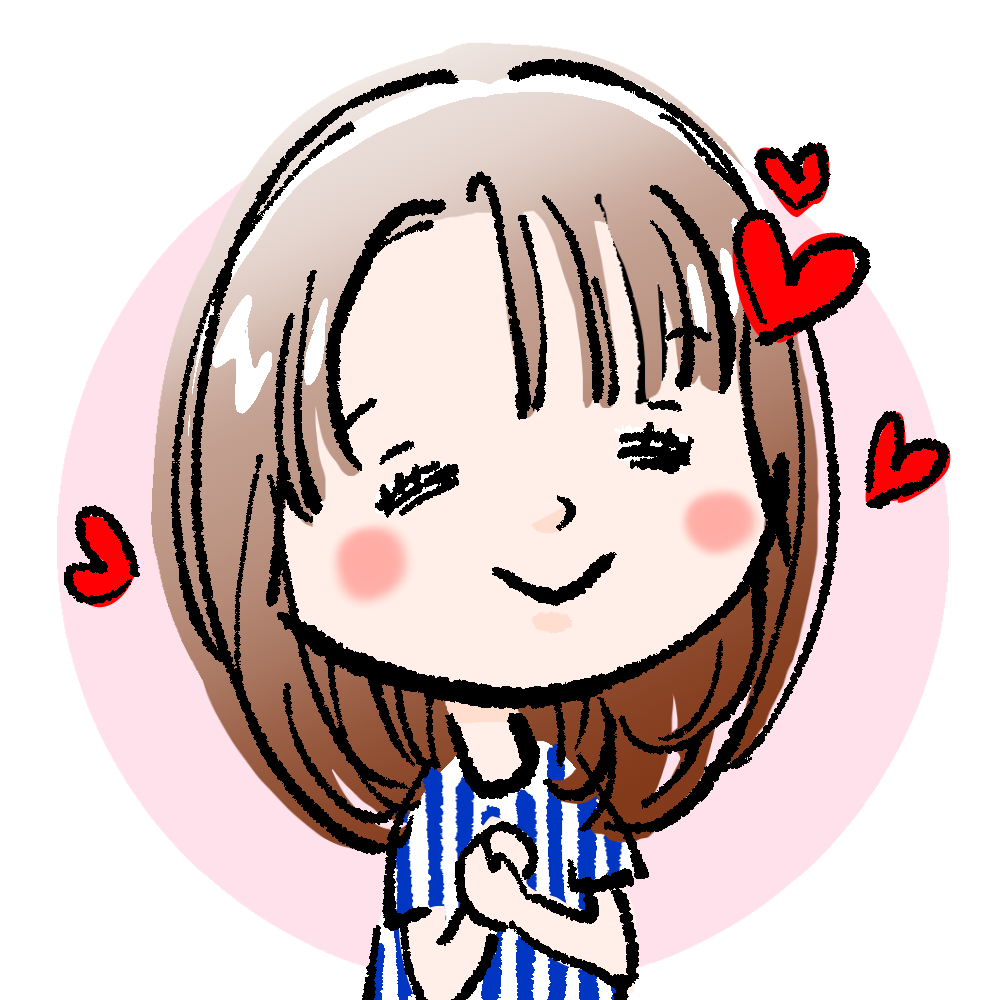
親に介護が必要になると、想像がつくと思いますが、必ず金銭面の負担が増えます。
2. キャリアの中断と再就職の難しさ
一度仕事を辞めてしまうと、再就職が難しくなる可能性があります。特に看護師の場合、ブランクがあると現場復帰に不安を感じる人も多いでしょう。
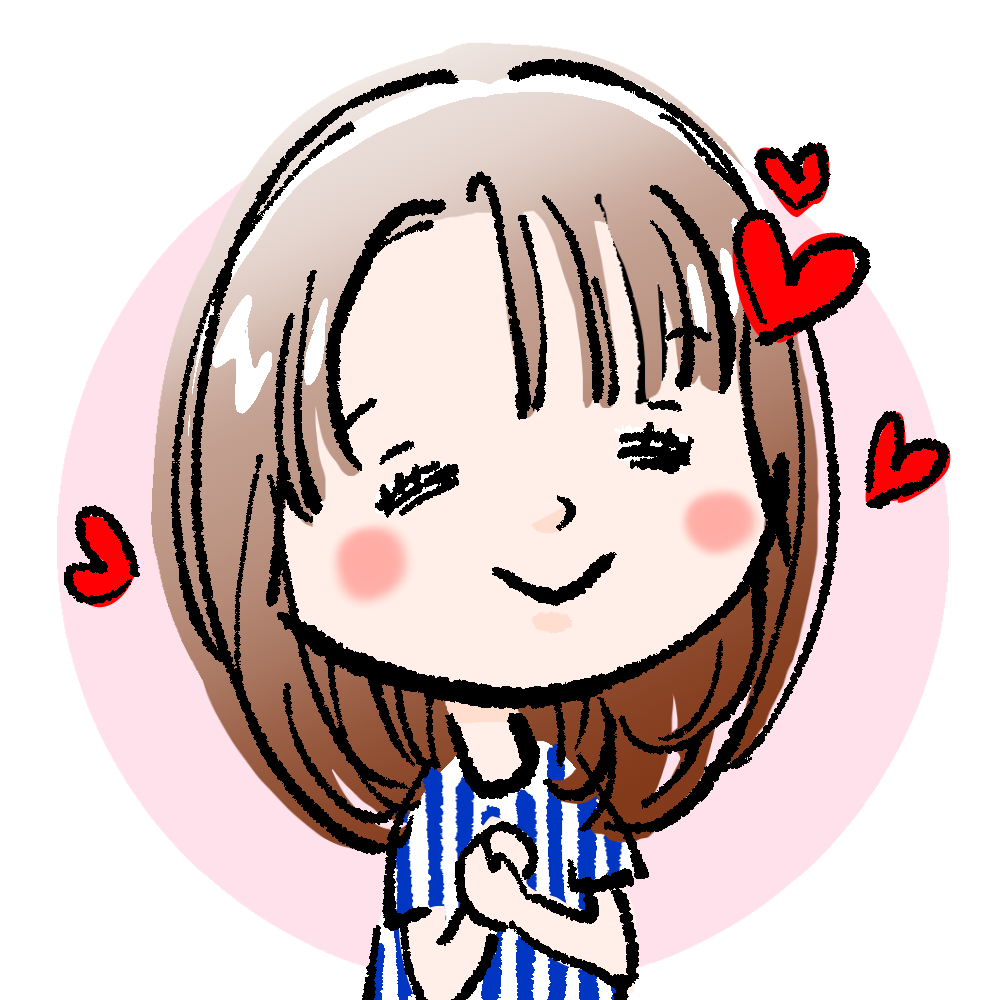
結果から言うと、再就職は可能なんです。医療や介護の現場は、人手不足に悩んでいるところが多いですから。ブランクが長くなることの方が心配です。
ただ、今まで自分がしたいと思ってやってきたことが、途中で途切れてしまうことで喪失感を感じるでしょう。働く環境が変わることでストレスが増えるのは間違いないでしょう。
3. 精神的・肉体的な負担が増える
介護は長期にわたることが多く、心身ともに大きな負担がかかります。仕事と介護の両立が難しくなり、結果として精神的なストレスが増大することも問題です。
介護はいつまですれば良いか誰にもわかりません。介護しないといけない人数が、一人と二人でも違います。
今の仕事をしながら、両立できるうちに、その後のことを見据えて動かないないと、八方塞がりになります。介護の手続きにも時間を取られます。
介護が視野に入ってきたら、その後は家族で介護する、サービスを併用して介護する、介護付き老人ホームなどを利用する...色々な選択が考えられますが、これもどんなものがあるのか知らなければ、選択の余地はありません。
看護師といってもみんなが介護制度に詳しいかといったらそんなことはありません。わたしも病棟で退院支援に関わっていたので、多少は分かりましたが、実際自分の家族のことになると調べながら手続きをすすめていくといった感じです。
ただでさえ仕事に追われ、時間に追われながら看護師として働いているのに、精神的にも肉体的にも負担が増えるのは必須です。
4. 家族間の負担のかたより
家族内で介護の負担が一部の人に集中すると、関係が悪化する原因になります。看護師として医療知識があるため、他の家族から「あなたがやるべき」と期待されることも少なくありません。
医療や介護のことを知っているので、介護の中心になってしまう可能性はとても高いです。そんな中、協力がないと全部押し付けられる可能性だってあります。
少子化が進む現代、家族形態は核家族や単身世帯が増加しており、ますますその傾向は強まる可能性があります。また、女性のライフスタイルも変化しており共働きが一般的になってきているので、親に介護が必要になった時に、どうするのかを家族で話し合っておく必要があります。
ひと昔前の考え方は「家族の問題は家族で解決する」そんな考え方がありましたが、現状では難しいと思います。一人っこや子供のいない家族では、社会資源を利用しないと解決できないことが多いです。
とっても難しいことですが、分かりやすく、利用しやすい社会資源が必要と思います。
介護離職を防ぐための解決策

1. 介護制度の理解と活用
日本には介護保険制度が整備されており、さまざまなサービスを利用できます。例えば、
- 訪問介護(ホームヘルプ):自宅での介護支援
- デイサービス:日中の見守りとレクリエーション
- ショートステイ:短期間の施設利用
- 特別養護老人ホーム(特養)やグループホーム:長期的な介護施設
これらを活用することで、介護の負担を軽減し、仕事と両立しやすくなります。
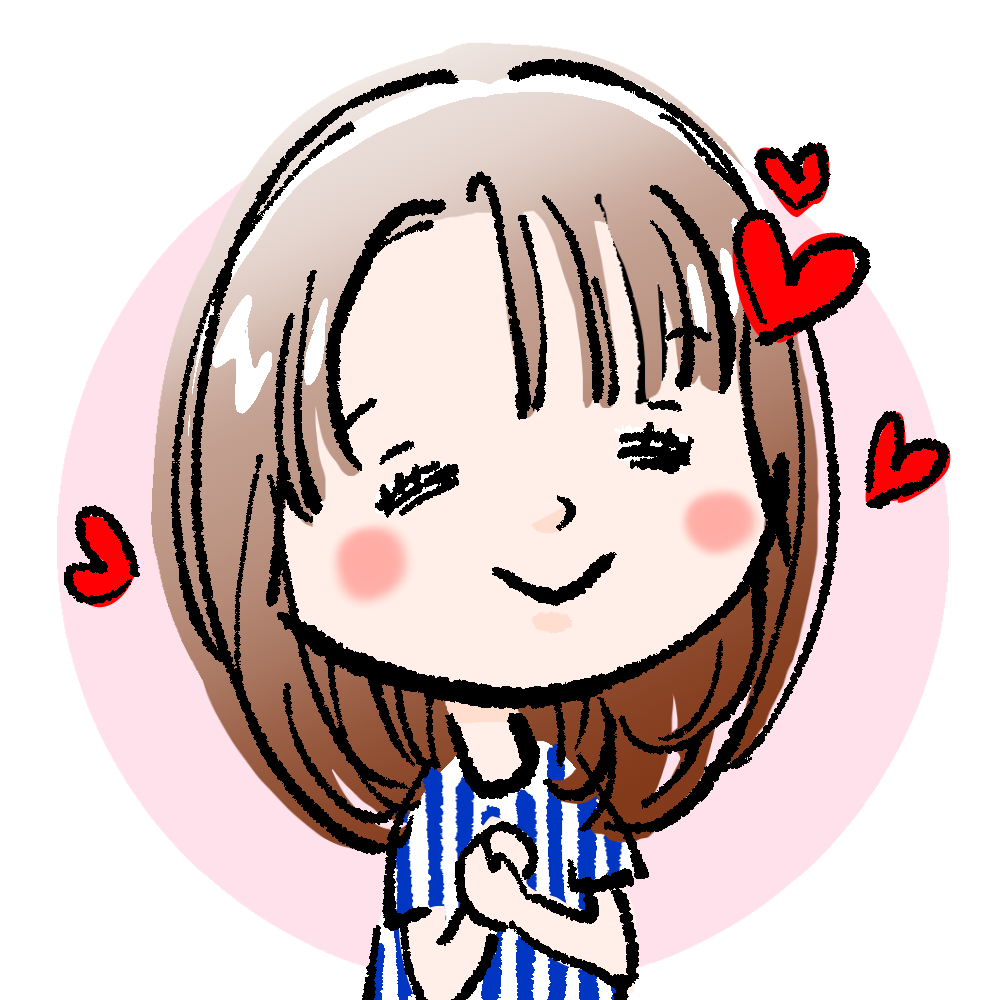
上記を使用するには、介護認定をしてもらう必要があるので、早めに調査をしてもらうことが大切です。「ちょっと一人で外出が難しくなったな」「体力が落ちてきたな」そんな気づきが必要です。
要介護認定とは、介護保険サービスを利用する際に必要な認定のことです。これを受けて認定された介護度によって実際に利用できる介護保険サービスが異なります。
要介護認定を受けて、認定がおりるまでの流れは以下のようになります。
この調査は、仕事をしながら早めに調査を受けておくことをおすすめします。これを受けてないと、職場の制度も使えないものが出てきます。
わたしは仕事を辞める前に、両親の介護認定調査を受けていました。介護が必要になって自己都合で仕事を辞めましたが、父が要介護1だったので、ハローワークで申し立てを行うことで、失業給付の待機の期間が短くなりました。
2. 職場の制度を活用する
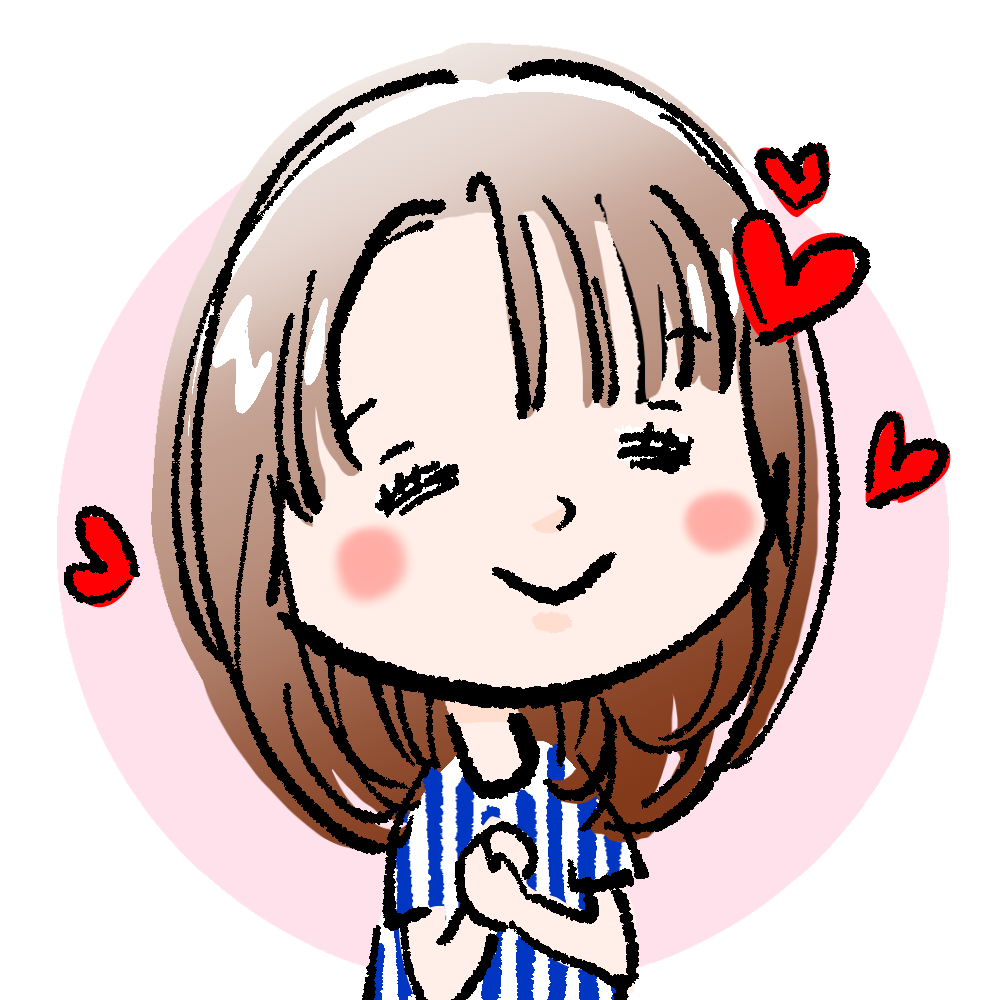
職場の制度を知らない看護師さんが多すぎます。また、知ってても使うのに抵抗がある人や職場自体が制度を理解していないことで、使えなかったという看護師さんもいました。
看護師の職場には、介護と両立しやすい制度が用意されている場合があります。知っていても、職場が人手不足だったり、休むことに罪悪感を持っている人は使うのに躊躇する人もいます。
育児休暇が広まって使いやすくなってきているので、どうか介護休暇ももっと認知され、使いやすくなって欲しいと思います。
- 介護休業制度:最大93日間の休業が可能
- 時短勤務・フレックスタイム制度:柔軟な働き方が可能
- テレワークの活用(可能な場合)
上記以外にも、介護休暇を利用して、通院やケアマネとの打ち合わせに利用するなどにも活用ができます。これらを使うにも条件があるので、調べておきましょう。
事前に職場の人事部や上司に相談し、どのような支援が受けられるか確認しておきましょう。
3. 家族との役割分担
介護は一人で抱え込まず、家族と協力して進めることが大切です。家族会議を開き、家族間の連絡体制についても話し合っておきましょう。例えば、
- 介護の役割分担
- 費用の負担
- 介護サービスの利用計画
など、はじめは大まかでも構わないです。介護が必要になってから考えるのではみんなが疲弊してしまいます。いずれ始まる介護の準備として話し合いの場を設けましょう。
4. 地域の支援サービスを活用する
地域包括支援センターでは、介護に関する相談を無料で受け付けています。自治体によっては、
- 介護者向けの相談窓口
- ボランティアや地域の見守りサービス
- 介護者向けの交流会や講座
なども提供されています。
地域包括支援センターとは、高齢者が住みなれた地域で安心して暮らせるように、介護や福祉、保健などに関する総合的な相談窓口です。
要支援や要介護の認定を受けているか受けていないかは関係ありません。一人暮らしで不安なことがある本人や、離れて暮らす親が心配な家族などが利用できます。
介護の備えとして活用することができます。
働きながらできる介護の準備
1. 早めに情報収集する
親や家族がまだ元気なうちから、会話をする機会を増やしてください。遠方なら電話やビデオ電話でもOKです。
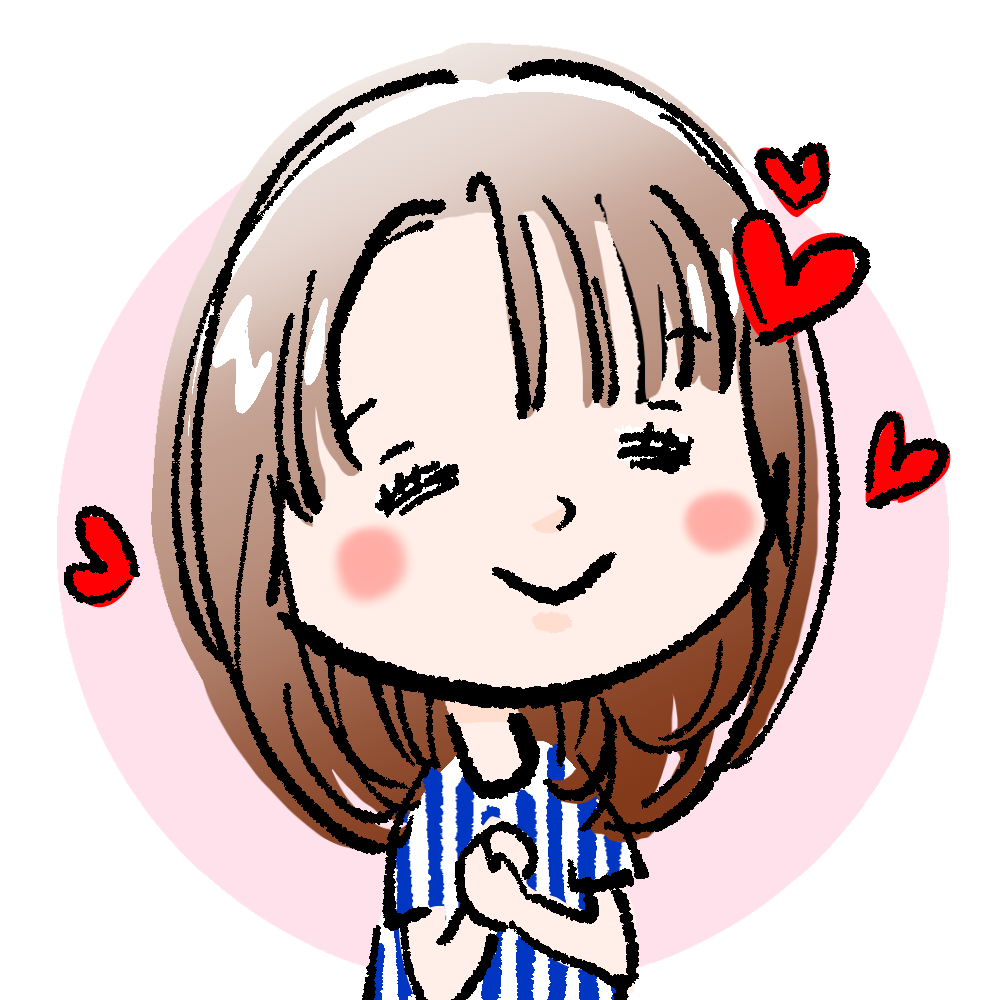
親は子供に迷惑をかけたくないと思って、困っていることがあっても、黙っていることも多いと思います。話す機会が増えると、ちょっとした会話から、得る情報もたくさんあります。
- 介護保険の申請方法
- 利用できる施設の種類と費用
- 親の健康状態や持病の確認
- 飲んでいる薬
- かかっている病院 など
を調べておくことで、いざというときにスムーズに対応できます。
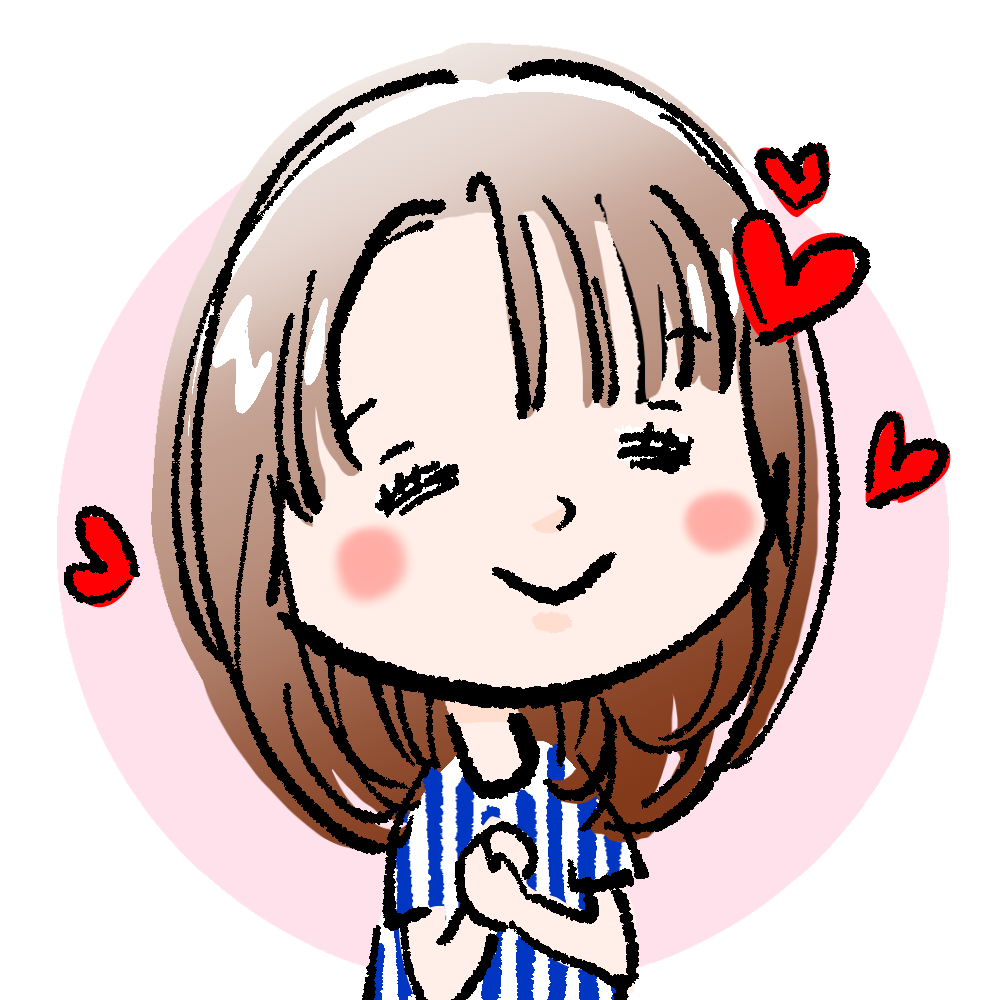
病院で勤めている時に、緊急入院で来られた家族の人が、他人かと思うくらい何も親のことを知らなかったのには、びっくりした記憶があります。普段、会話をしていても、肝心なことは話していないんですね。看護師のあなたなら、アセスメント力を発揮して、意図的に情報収集してくださいね。
2. 貯蓄・資金計画を立てる、概算を把握する
介護には予想以上にお金がかかるため、
- 介護費用の試算
- 貯蓄の強化
- 保険(介護保険・医療保険)の見直し
を行い、経済的な準備をしておきましょう。
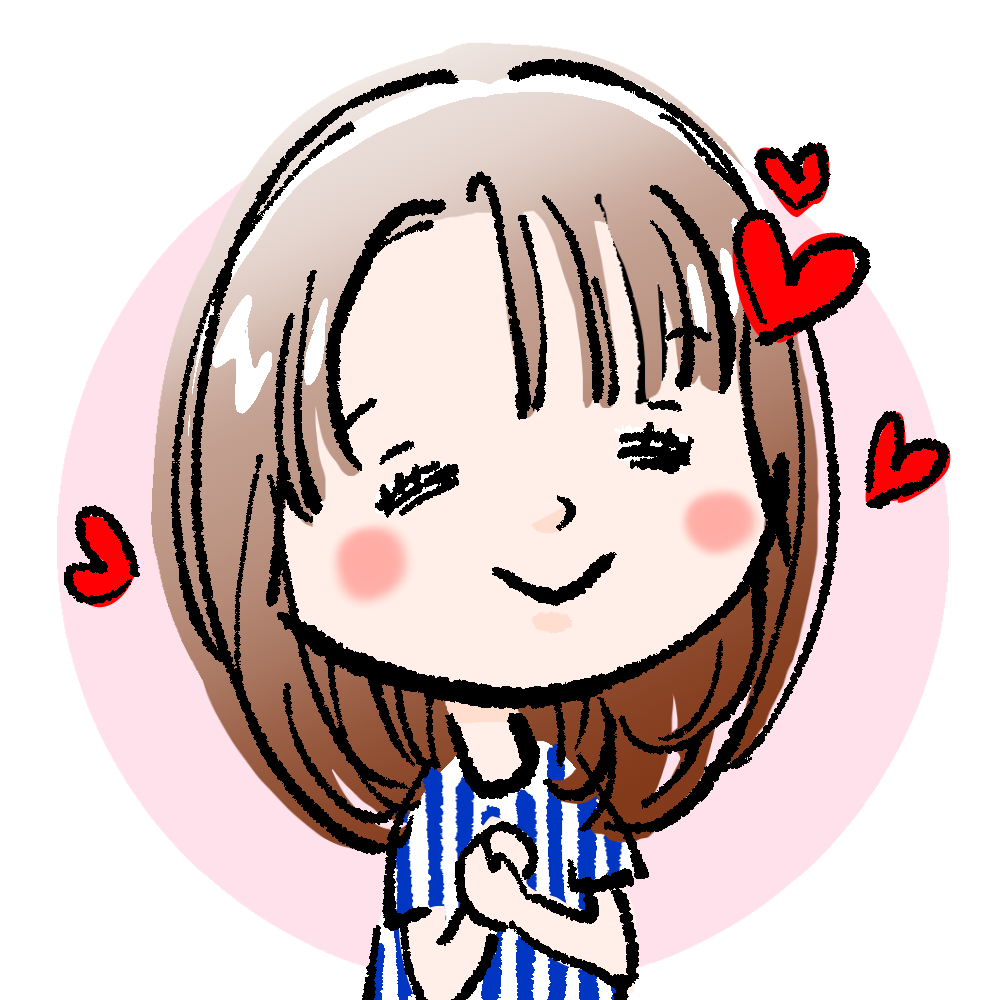
さすがに、面と向かって「今、貯金いくらあるの?」なんて親に聞けないですよね。急にそんなことをいったら、家族のトラブルの原因にもなりかねません。
でも、大事なことなんですよね。
高齢の親は、自分が入っている保険のことを意外に何も知らないことも多いし、見直しもしていないことが多いんです。「保険に入ってるから大丈夫」って思っている人が多いのは事実です。
そして銀行も何個も取引していることが多いです。一つにまとめる準備をした方が良いです。解約手続きにとても時間を取られるケースがあります。
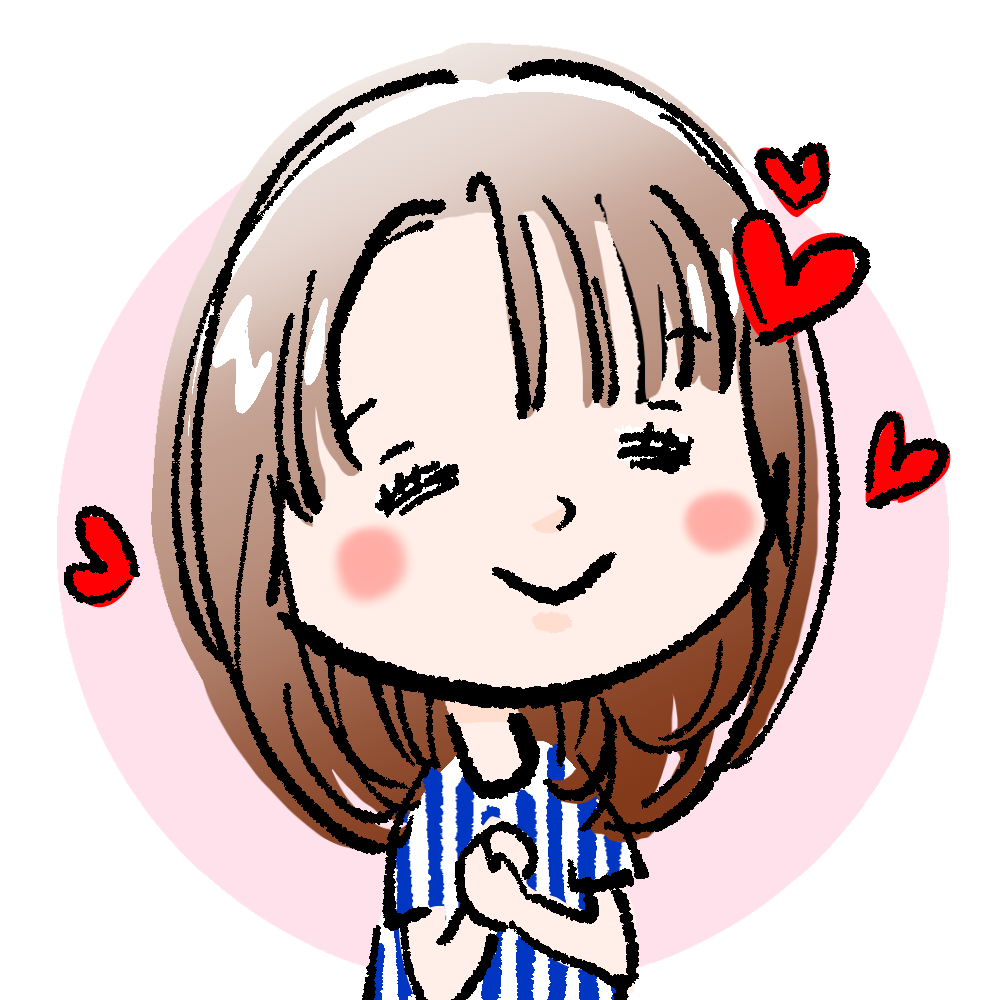
わたしの親の通帳を一つにまとめるために、解約したい銀行にいったら、「予約はお取りですか?」から始まって、直筆で名前と住所を書いてくださいと。高齢でメガネがないと見えないし、細い枠の中に自分の名前を書くのもやっとなのに、長い住所を書こうと思うと至難のわざでした。間違えると初めから書き直し。結局、2時間半、銀行にいました。もう少し若い時に連れて行けてたら、お互いにこんな苦労しなくてもよかったのにと思います。
3. 介護に役立つスキルを学ぶ
看護師としての知識を活かしつつ、情報網は広げておきましょう。看護師だから介護のこともわかっているだろうと思われがちですが、全員が詳しいわけではありません。
- 介護技術(移乗、食事介助など)
- 認知症ケアの知識
- 介護福祉士などの資格取得
を進めておくと、より負担の少ない介護が可能になります。
あとは、時間のある時に親に断捨離の話をして、整理してもらうことも必要です。
いざベッドを利用しようとしても、荷物に溢れてて片付けからしないと入れられないってことも十分にあり得ます。
4. ワークライフバランスを意識する
介護と仕事を両立するためには、自分自身の健康管理も重要です。仕事以外に気になることが増えると、それだけで疲れがどっとでます。夜勤などをしながら不規則な生活をしていたら、尚更です。
- 睡眠や休息をしっかり取る
- ストレス発散の時間を確保する
- 必要ならカウンセリングを利用する
など、心身のケアも忘れないようにしましょう。
まとめ
看護師が介護離職を避けるためには、早めの準備と周囲の協力が不可欠です。介護制度や職場のサポートを上手に活用しながら、家族と協力し、無理のない形で介護を進めることが重要です。仕事を続けながら介護を乗り切るために、今できることから始めてみましょう。